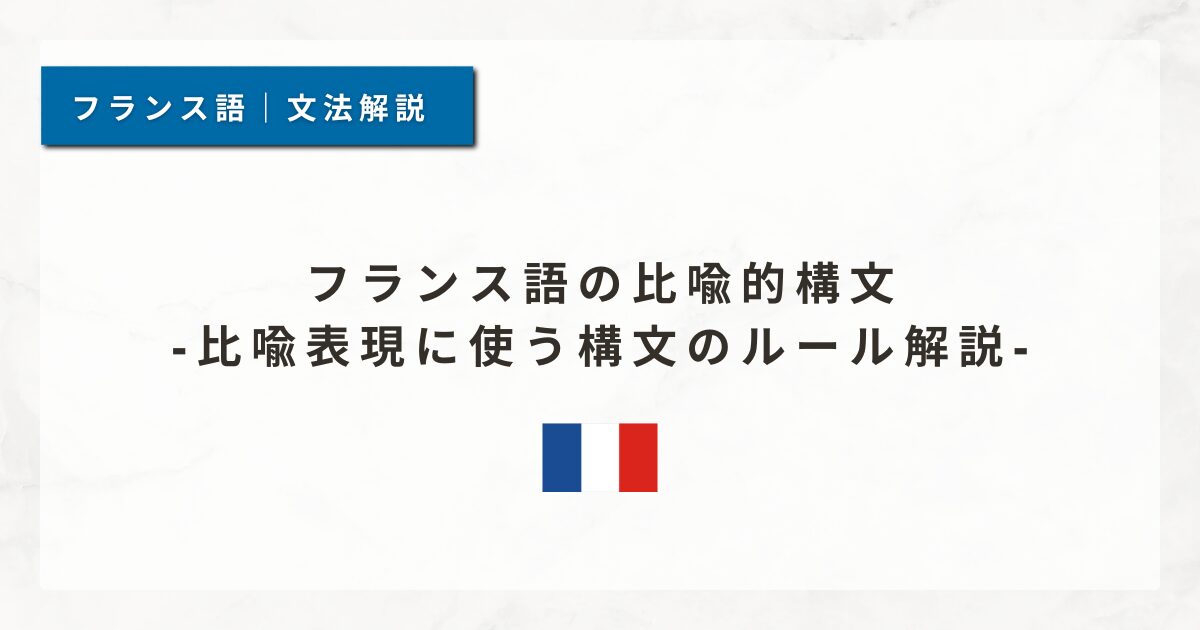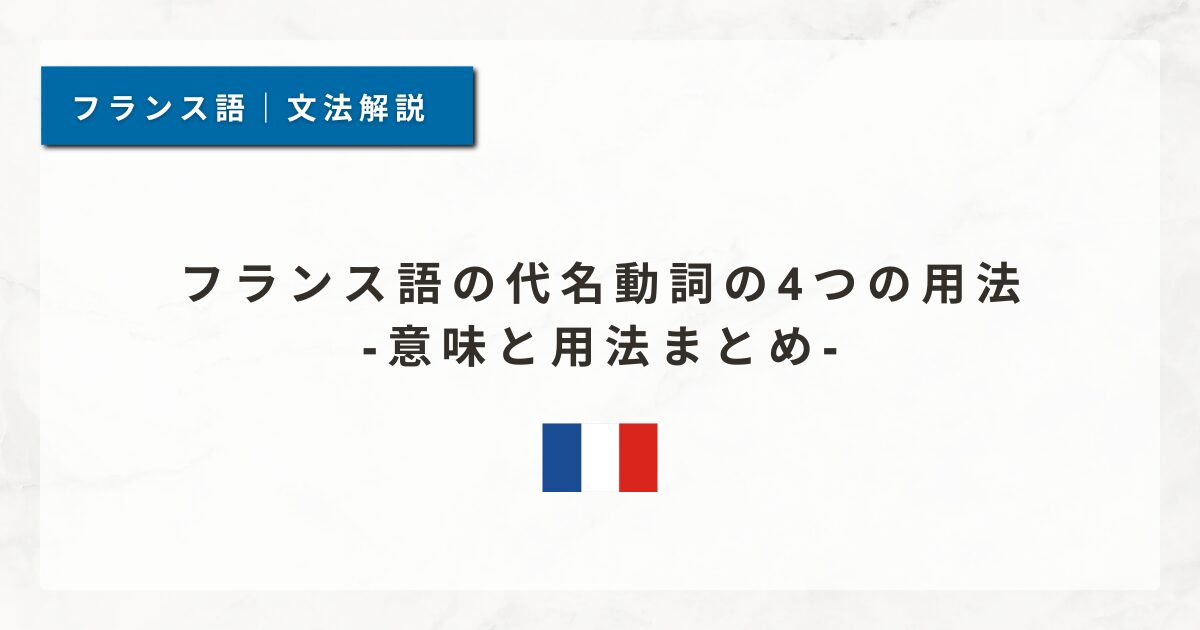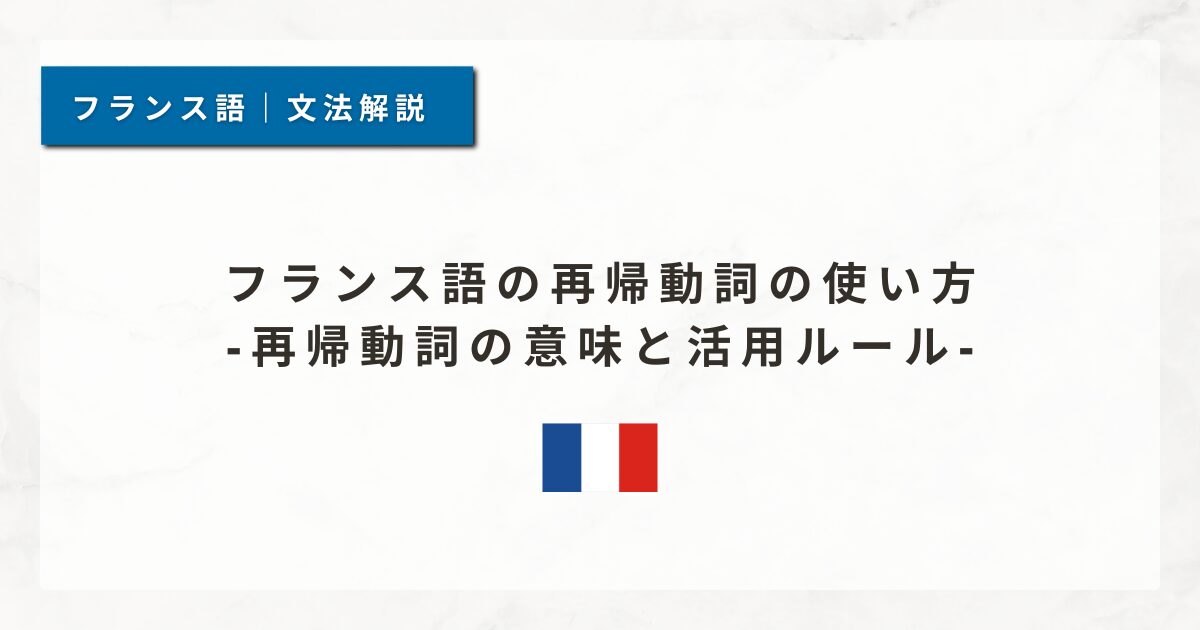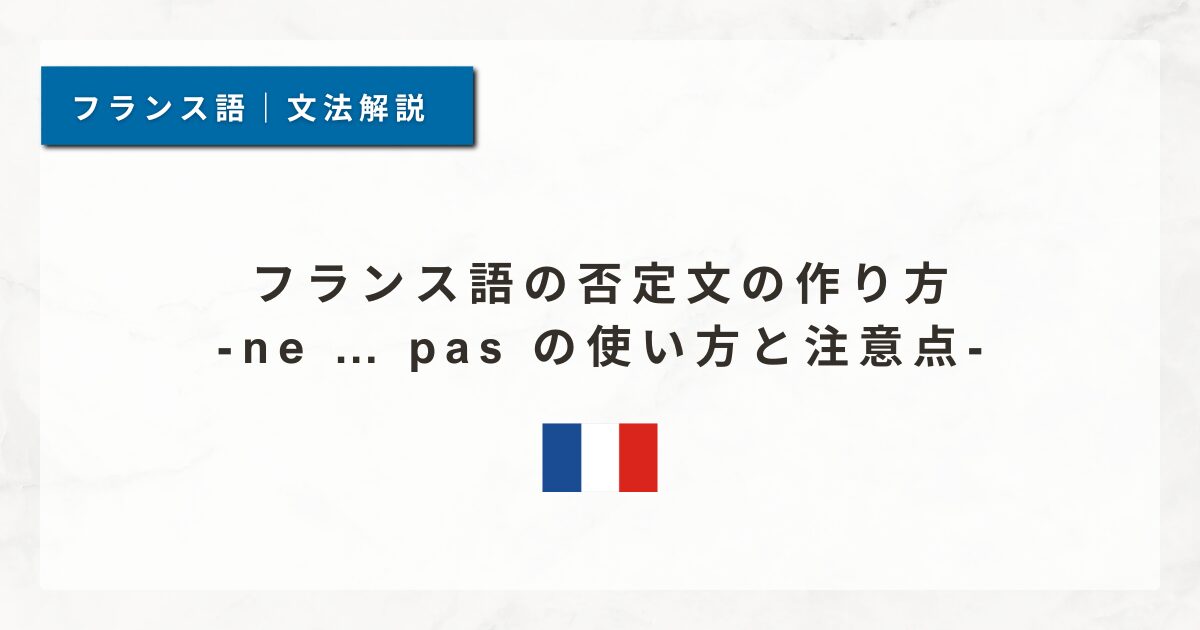#73 フランス語の接続法大過去|活用ルールと用法まとめ
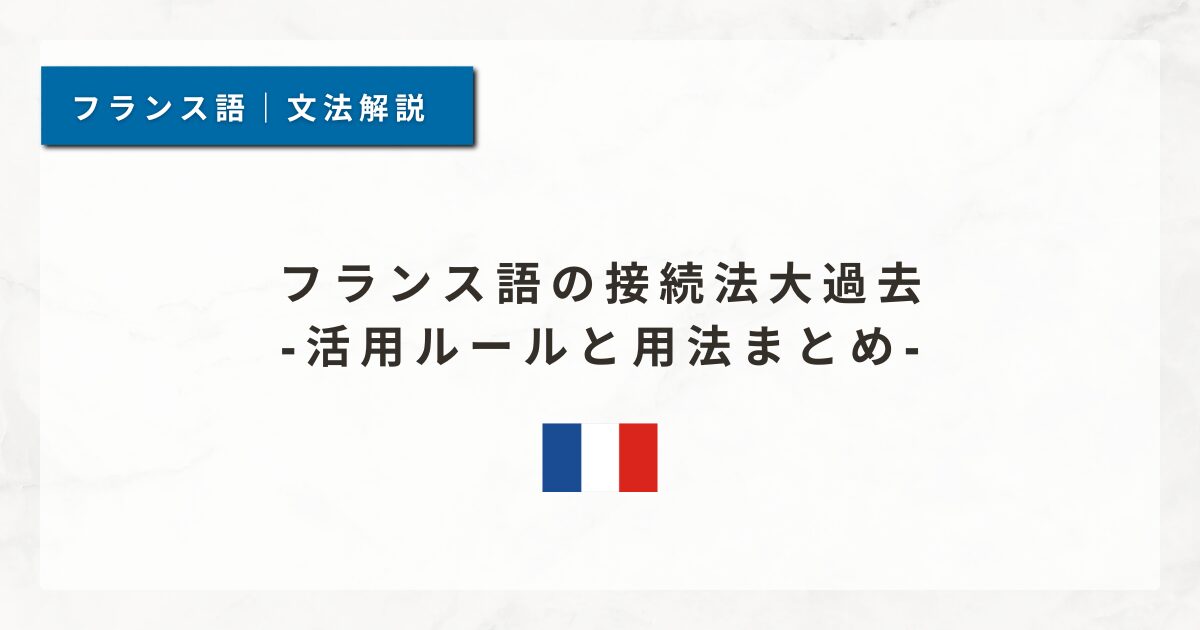
接続法大過去は、フランス語の接続法の中でも形式的かつ古風な時制です。
現代フランス語の会話では使われず、ほとんどの場面で「接続法過去」に置き換えられます。
そのため学習の優先度は低いですが、文学作品や歴史的な文章、古典劇などでは今でも見られるため、読解力を高める上で理解しておくと有利です。
今回は、接続法大過去の文法的特徴や使い方について解説していきます。
1. 接続法大過去の作り方
接続法大過去は、「助動詞(avoir / être)の接続法半過去形+過去分詞」で作られます。
構造自体は「大過去」や「条件法過去」と似ていますが、助動詞が接続法半過去形を取り、その活用形が少し独特となっています。
- que j’eusse parlé
(私が話していたとしたら) - qu’elle fût arrivée
(彼女が到着していたとしたら)
avoir / être の接続法半過去である eusse/ fusse という形は、文学作品でしか見られない特有の活用です。
現代フランス語では eusse, fusse は稀にしか登場しないので最初は違和感がありますが、繰り返し目にすると「あ、接続法大過去だ」と気づけるようになります。
2. 接続法大過去の用法
接続法大過去は「過去における仮定」「過去完了のニュアンス」を示す際に使われます。現代では同じ意味を接続法過去で表すのが一般的です。
2-1. 過去の非現実条件を表す場合
現実には起こらなかったことを、仮定的に述べるときに使われます。
- Je ne croyais pas qu’il eût compris la situation.
(私は、彼が状況を理解していたとは思っていなかった)
現代では “Je ne croyais pas qu’il ait compris la situation.”と表すのが一般的です。
2-2. 主節が過去に属する場合の従属節
文章全体が過去に属する場合、接続法大過去が従属節で現れることがあります。
- Il doutait qu’elle fût arrivée avant lui.
(彼は、彼女が自分より先に到着したかどうか疑っていた)
こちらの例文も、“Il doutait qu’elle soit arrivée avant lui.” と接続法過去を使う方が自然です。
3. 接続法過去との比較
現代フランス語では、接続法大過去は実質的に接続法過去に置き換えられています。
- 接続法過去(現代で使用):
例:Je ne crois pas qu’il ait compris la situation.
(彼がその状況を理解したとは思えない) - 接続法大過去(古風・文学的):
例:Je ne crois pas qu’il eût compris la situation.
(意味は同じ。ただし古典的な表現)
つまり、接続法の過去と大過去に意味の違いはなく、あくまで文体上の選択となります。
接続法大過去は会話ではほぼ使わないので、暗記の優先度は低いです。ただ、読解用に知識を持っておくことは大切で、特に古典文学・戯曲・歴史的文書を読むときに役立ちます。
4. まとめ
- 接続法大過去は「助動詞(接続法半過去形)+過去分詞」で作ります。
- 過去の仮定や従属節で使われますが、現代では接続法過去に置き換えられます。
- 現代フランス語では会話で使わず、文学作品・古典劇・歴史的文章にのみ登場。
- 基本的には接続法大過去は無理に覚える必要はなく、出てきた時に理解できれば十分です。